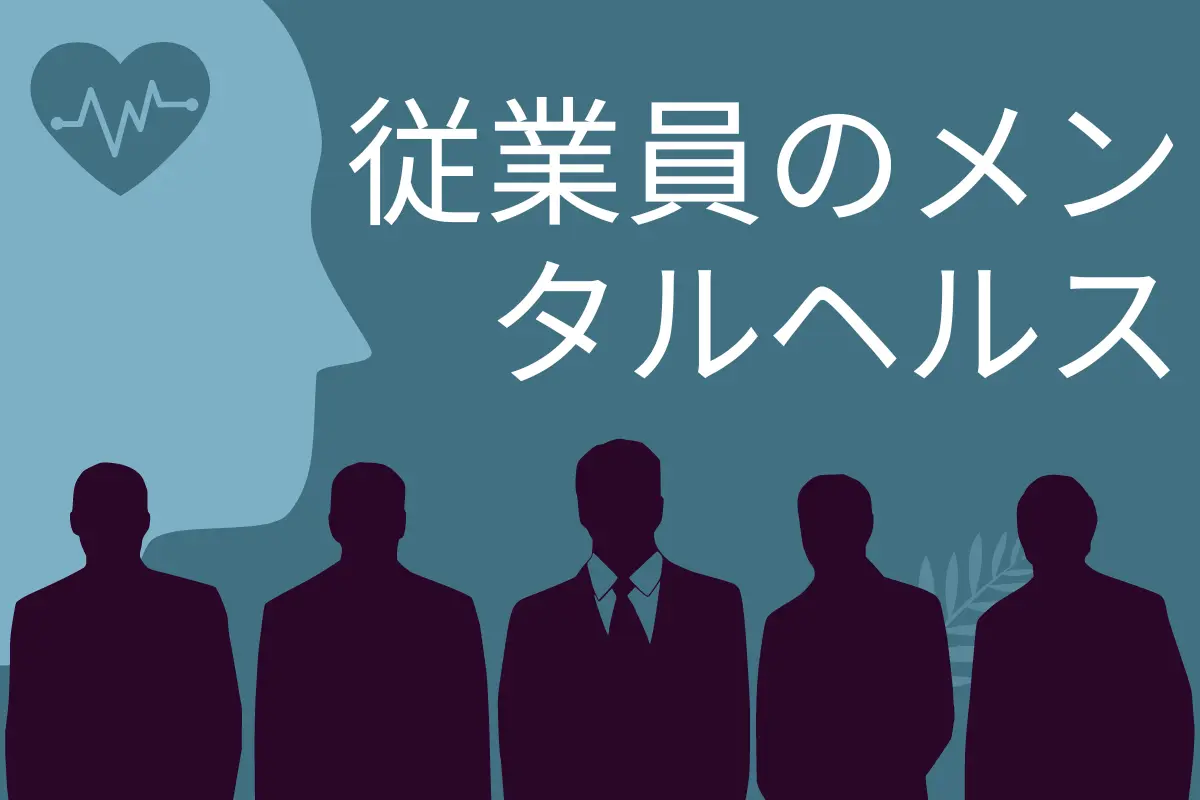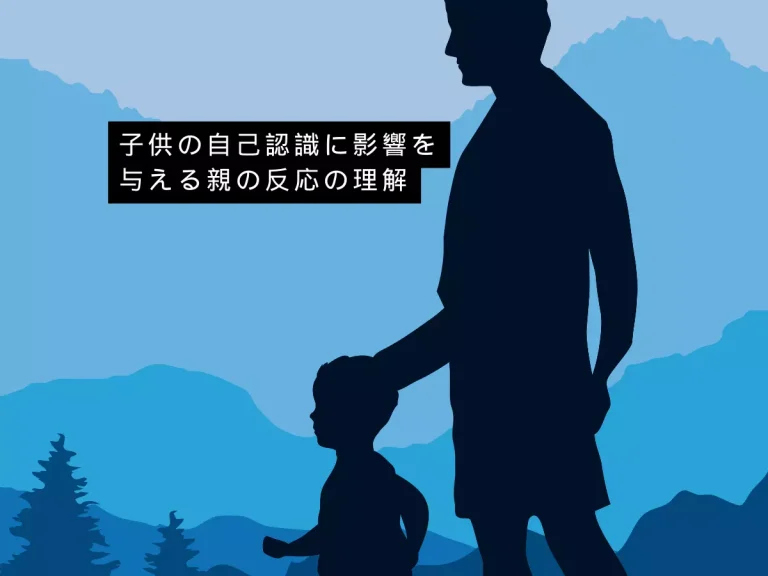メンタルヘルスを自覚する従業員とその管理:成功するための戦略
メンタルヘルスの第一原則:業務遂行能力の判断
生産性の観点からの判断
従業員が自身のメンタル状態を自覚している場合、その従業員が業務を遂行できているかどうかが最初の判断基準となります。生産性が問題ないと判断される場合、その従業員は働き続けることが可能です。しかし、業務遂行レベルが50%以下を明らかに下回っている場合、その従業員を休ませ、他の従業員がその部分をカバーすることで部署全体の生産性を維持することが可能です。
就業規則の観点からの判断
次に、従業員が就業規則を満たしているかどうかを人事部が判断します。就業規則には「正当な理由なくたびたび離席してはならない」「上司の命令に従う」などの規定が含まれています。これらの規定を守れていない従業員は、就業規則違反となります。
ストレスは精神的な問題を引き起こす可能性があるため、ストレスを軽減することが重要です。
メンタル異常の従業員に対する一般的な対応
放置や無視の問題
メンタル異常を自覚している従業員に対する一般的な対応は、「放置」や「無視」が多いです。しかし、これは問題です。管理者は、従業員のメンタル状態を理解し、適切な対応を行う責任があります。
メンタル不調と処分の関係
メンタル不調であるか否かによって、処分を行うかどうかを決定するのは適切ではありません。メンタル不調の判断はグレーゾーンがあり、主治医にとっても難しいものです。メンタル不調であろうがなかろうが、「業務を遂行できているか否か」で働かせるか休ませるかを判断するのがシンプルです。
メンタル不調の判断と業務遂行能力
メンタル不調のグレーゾーン
メンタル不調の判断は、主治医にとっても難しいものです。メンタル不調の状態は人それぞれ異なり、一概には判断できません。そのため、業務遂行能力を基準にすることが重要です。
業務遂行能力の判断基準
従業員が業務を遂行できているか否かは、その従業員が働き続けるか休むかを判断する最もシンプルな基準です。メンタル不調であろうがなかろうが、この基準に基づいて判断を行います。
健康上の問題と業務遂行能力
健康状態の観察と推測
管理者として、従業員の健康状態を観察し、推測することが重要です。顔色が悪い、肩で息をしている、意識がぼーとしているなど、従業員の健康状態を推測するための観察ポイントは多数あります。
健康上の問題を見落とした場合の対応
仮に管理職が従業員の健康上の問題を見落としたとしても、その従業員がそれを我慢していわずに業務を遂行できていたとすれば、安全義務違反には問われません。
結論:メンタル異常を自覚している従業員の管理
メンタルヘルスの管理の重要性
メンタルヘルスの管理は、従業員の健康と生産性を維持するために非常に重要です。管理者は、従業員のメンタル状態を理解し、適切な対応を行う責任があります。
管理者の役割と責任
管理者は、従業員のメンタル状態を理解し、適切な対応を行う責任があります。また、従業員の健康状態を観察し、推測することも重要です。これにより、従業員の健康と生産性を維持することが可能となります。